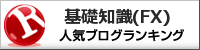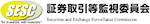僕が昔、先物取引会社に務めていた頃、トレーダーの上司から「相場の局面ごとの、取るべき基本的なトレード手法」について徹底的に叩き込まれました。
その中には、ナンピンについての考え方もあって、かなり重要なトレードテクニックとして扱われていたことを覚えています。
ちなみに、ナンピンとは「難を平らげる」と書いて難平(ナンピン)と読みます。
「ナンピンとは何か?」を簡単に説明すると、仮にドル買い円売りのポジションを取ったあと、相場が思惑とは逆に行き、含み損を抱えてしまったような状態の時、「下がったドルをさらに買い増し」し、平均買付け価格を下げることで、とりあえず、「今ある難から逃れる」手法のことです。
ナンピンは厳禁ではない

世間では、書店に溢れる「トレード本」の多くが解説しているように、「ナンピンは取ってはいけない手法」として紹介されていることがほとんどです。
「ナンピン厳禁」とまで書いている本もたくさんあります。
理由としては、「ナンピンは傷を深める危険がある」からです。
確かに、そもそも取ったポジションに対して相場は逆を行っているわけですから、さらにポジションを積み増す行為は、傷を深める可能性が高い行為に違いありません。
資金管理の出来ていないトレーダーが、苦し紛れにナンピンを繰り返したりしていては、最悪の場合、あっという間に証拠金維持率を下回って「即、退場」ということにもなりかねません。
それほどリスクのあるトレード手法だけに、ナンピンを「絶対に取ってはいけない手法」と説く書籍や「ネットのトレード先生」が、数多くいるわけです。
僕自身も、戦略のない「ただ精神的な苦しさから逃れるためだけのナンピン」は、間違ったトレード手法だと思っています。
しかし、当初から「相場が逆を行った場合は、下の価格で買い増しする」と決めて買い増しをする、トレード手法があるんです。
その手法はナンピンとは「似て非なるもの」で、「買い下がり(逆は売り上がり)」と呼ばれる、プロトレーダーたちが当たり前のように使っているトレード手法です。
ナンピンではない戦略的「買い下がり or 売り上がり」の前提は分割売買

ここでまず前提となるのは、「そもそもみなさんはトレード資金をきちんと『分割』して売買しているでしょうか?」ということです。
FX初心者や、負けてばかりいるトレーダーの多くは、資金を分割せず、ひとつのレートに「一点張り」する傾向が見られます。
資金量の大きい小さいに関わらず、プロトレーダーはひとつのレートに一点張りするようなことはしません。
たとえ少額のトレードであっても、資金を分割して戦略的にトレードを組み立てます。
その理由は、仮に、ひとつのレートにすべての資金を突っ込んだとします。
その後、相場が思った通りに行ってくれればいいんですが、もし、逆を行かれたらどうしましょう?
もうすでに資金は全額投入してしまっています。
この場合、出来ることといえば神頼みぐらいです(笑)。
これでは戦略もなにもありません。
ただのギャンブルと同じです。
プロトレーダーは、そんな無謀なトレードは絶対にしません。
プロトレーダーのトレードとは、ポジションを取ったあと、相場が思惑通りに行こうが、逆を行かれようが、どちらのケースも想定したうえで、対処できるよう、戦略を組み立てているものです。
その場合、前提となるのは、前もって投入可能な資金を「分割」しておくことです。
そうしておけば、仮に相場が思っていたのとは違う方向に動いたとしても、その状況に合わせた対処方法を取ることが出来ます。
プロトレーダーのトレードとは、レートが下がることを想定して、まず試し玉で買いを入れ、思ったレートまで「予想通り」下がったら、本玉を入れて行きます。
こういった、下がることを想定して買いを入れていくトレード手法を「買い下がり」と呼ぶのですが、その際に、
「試し玉を入れたあと、相場が上に行ってしまった場合はどうするのか?」「少額しか入れてないので儲けが少なくなるじゃないか」
といった質問をよくされます。
この質問に対して、僕はいつも、
「確かに、試し玉の段階で相場が上に行ってしまえば、儲けは少なくなります。でも、プラスなので問題ありません。」
と答えています。
試し玉は、本玉を入れるレートまで下がってきてくれなかった際の保険のようなものなので、狙って取りに行くものではないんですが、それでも儲けが出たわけですから、ラッキーなことと受け入れておけばいいと思っています。
FXで生き残るのに必要なことは、大負けをしないことです。
1回のトレードの儲けが多少すくなくなったとしても、勝ちで終えられるなら問題はありません。一攫千金を狙うよりも、損失額を限定し、勝つ確率を上げることの方が、戦略としては重要になってきます。
ナンピンではなく、戦略的買い下がり(売り上がり)で勝率は格段にアップする
では、「苦し紛れのナンピンではない、戦略的買い下がり」がどんなトレードなのか、すこし具体的に見ていきましょう。
ここで例に挙げるのは、僕が以前、毎日更新していた「トレード日記」の2017年8月25日のトレードです。
実際の僕のトレードから例えを引用した方がリアリティがあって良いかと思い、過去のトレード日記から「買い下がりの場面」を探してきました。
ただ、トレード日記用のトレードは「見せるためのもの」なので、僕の普段のトレードスタイルである「5分から2、30分持つトレード」ではなく、スキャルピングに近いものです。
スキャルピングのような、超短期の売買では、基本的に「買い下がりや売り上がり」といった手法を取らないので、トレード日記のトレードから引用するのは適切ではないかもしれませんが、とりあえず「買い下がり(売り上がり)」の雰囲気は掴んでいただけるかと思います。

実際に「買い下がり」のトレードをしているケース。
上のチャートを見てください。
この日の最後のトレードとなった4番目のトレード。このトレードで、僕は「買い下がり」を実践しています。
直近のローソク足の動きは「上方向」。かつすべての移動平均線とサポートレジスタンスラインの上で相場は展開している状況です。
このケースは、基本的に「上目線」で構えていて良い局面です。
なので、「上目線」の前提が崩れない限りは、下がってきたレートは「すべて買って行っていい場面」と言えます。
そうした条件が整った中で実践したのが、この時の「買い下がり」です。
ちなみに実際に取引した証拠というか、証券会社の売買履歴が下(↓)の画像です。
上のチャートで買い下がった場面は、④の一連の売買になります。

④のトレードが、買い下がりでポジションを作っている場面。
「上昇局面の中の下げの場面」で、積極的にロング(買い)のポジションを積み増して行っているのが分かります。
これが、「買い下がり」と呼ばれるトレード手法です。
江戸時代の米相場師の基本は2・3・5の買い下がり

上の実例では、「買い下がり」のトレードがどういったものなのかを確認できました。
ただ、スキャルピングに近いトレードだったので、伝統的な買い下がりとはすこし違ってしまっています。
実は、買い下がり、あるいは売り上がりといったトレード手法の起源は古く、江戸時代の米相場で、当時の相場師たちが編み出した手法なんだそうです。
その際、彼らが使っていた買い下がりの方法は、「2・3・5の分割」による買い下がりだったそうです。
つまり、試し玉が2、本玉が最後に5、その中間に3を入れる手法です。
これが本来の買い下がりの手法
この江戸時代の相場師の手法を簡単に説明すると、
本当は狙った価格(レート)まで下がるのを待って、全額10を入れたいのですが、そこまで下がってくるかどうか分からないので、最初に反発しそうなところで試し玉2を入れます。
次に、反発する可能性の高い価格で3を入れ、それでも反発せず、当初の想定通りの価格まで下がってきたら、いよいよ本玉の5を入れます。
まとめ
ひとつのレートで投資資金のほとんどを一点張りするようなトレード手法では、ナンピンが「厳禁」なのは間違いないでしょう。
しかし、ここで解説してきたように、「レートが下がることを前提に買い下がる」トレードをすれば、それだけで勝つ確率を確実に上げることが出来ます。
この手法も、レートが下がったあとに買い増すという意味では、ナンピンと捉える人もいるかもしれませんが、当初から買い増すことを想定し、戦略的にポジションを作っていくので、いわゆるナンピンとは区別して考える必要があります。
戦略的に、下がったレートでポジションを積み増していく手法は、江戸時代からその有効性が証明されている確度の高いトレード手法です。
ぜひ、皆さんには、「ナンピンは厳禁」と下がったレートで買い増すことを拒否せずに、戦略的にレートが下がったところを狙いに行って欲しいと思います。
きっと、あなたのトレード成績は飛躍的に伸びることでしょう。
おすすめ記事海外業者でFXを始める手順【元先物トレーダーが解説】
おすすめ記事プロトレーダーが実戦で使っているFX会社